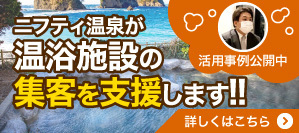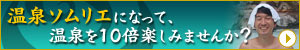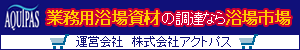口コミ一覧 (口コミ最新投稿日:2020年6月1日)
-

旅行ガイドブックと、インターネットのクチコミに惹かれて立ち寄りで利用しました。混浴の露天はあまりにも開放的で一瞬躊躇しましたが、誰もいない貸切だったこともありゆったりと湯浴みを楽しみました。
4つ(うち1つは女性専用でしたが)ある外の湯船は、温度が微妙に異なりましたがいずれも下からぼこぼことお湯が湧き出て、真っ白な非常に濃い硫黄泉に感激しました。あとで、男女別の内湯と露天にも入りましたが、こちらは加水されているのか混浴露天に比べて少し薄いような気がしました。
快晴のもと、八幡平の頂上までトレッキングした汗を気持ちよく流すことができました。0人が参考にしています
-

東北最高所の温泉。そのキャッチフレーズにひかれ、7月6日訪れた。入浴料600円を払って男女別に分かれた内湯と露天へ。
ドバドバと惜しげもなく注がれる源泉。泉温が98度と非常に高いので加水して温度を下げてある。ところが、内湯はそれでも熱くてとても入れないほどであった。
露天は適温。左手にはアスピイーテラインが優雅な曲線を描くのが見え、右手には岩手山が見える。雄大な大自然を見ながらの湯浴みは最高である。
ここにはもう一つ混浴の湯船もある。正反対の場所にあり、湯守りの人の話では、湯加減がすごく難しいとのことだった。脱衣所の清潔感が今一。ちょっとした気配りで変わると思うのだが…。1人が参考にしています
-

-

8月のお盆の前に日帰り入浴をさせていただきました。
野趣というのはこういうものをいうんでしょうか!
すごい強烈なお湯!景色も素晴らしい!
観光バスでの入浴客もいて芋洗いのように混んでいました。
混浴は女性にはちょっと敷居が高いかも?1人が参考にしています
-
暴風雨の岩手山から下山してきて、藤七温泉に宿を借り、冷えた体を温めました。
みなさんのクチコミ通り、混浴露天風呂の開放感と、源泉掛け流しの白濁した酸性の湯、すばらしかったです。
夕食は食堂でがやがやといただきますが、地元の山菜やキノコ、豆腐などの素材がおいしく、天ぷらや焼き魚も暖かいものが出てきて、豪華ではありませんが素朴で満足できました。
そして夕食時の従業員のお話。方言を駆使して、宿の案内や周辺の紹介を、おもしろおかしく語ってくれて、みな大爆笑でした。これだけは日帰り入浴では見れません(2006年9月宿泊)。1人が参考にしています
-

混浴露天風呂ですが、夜だけでなく、早朝にも女性専用の時間帯を設けてほしいと思いました。
それから露天には屋根がないので、雨の日は、よっぽど根性がなければ入れません。屋根か何かあればいいのですが。
食堂が黴くさいのが気になりました。
昼食の野菜バイキングはおいしかったです。1人が参考にしています
-

五月に宿泊してすっかり気に入り、8月16日に、立ち寄りで入浴いたしました。連れは、足元涌出の露天風呂がすっかり気に入ったようで、案内をした甲斐がありました。私は、見晴らしの良い露天風呂でリラックス。昼食に地元野菜をふんだんに使った、野菜バイキングみたいなのがありました。時間的にあわなかったので、食べませんでしたが、すごく気になりました。残念・・・・・・・
2人が参考にしています
-
観光バスが入ったばかりで 少し引きましたが
露天風呂で岩手の山を眺めながら 自分の世界を展開してまして
気が付くと 貸し切りになっていました。
静かな内湯にも入りたかったのですが時間の都合で断念(>_<)
4点にしたのは 足下湧出の岩風呂が未体験だからです。
次回は宿泊しなくてはと決意させる湯でございました。
ちなみに画像の上段の湯舟は、湧き水で加水してました。1人が参考にしています
-

3年ぶりに宿泊しました。以前も内湯から続く露天風呂以外の外側に露天風呂(野湯っぽいもの)がありましたが、それが今回行ってみると4つにも増えていました。お湯の温度もぬる目から熱目まであって楽しめました。野趣あふれる温泉に大満足でした。夕食のときの宿の担当者の話は方言丸出しのとても惹きつけられる面白い話だったこともいい思い出になりました。
1人が参考にしています
-

-

機会を得て、念願の藤七温泉を訪れました。下界は木の下闇の日に日に濃くなる時候なのに、八幡平はまだ雪景色!
テレビはロビーの一台が衛星放送のみを映し、携帯が通じないのも覚悟していましたが、公衆電話がないとはっ! 北海道の山の山の中の温泉でも公衆電話はありました。 でも、その遠さがご馳走です。
お湯は素晴らしい。 白濁の温泉はやっぱりいいですね。
翌朝には、露天風呂からご来光を拝む事が出来ました。宿泊客は私らを含めて、五人。 朝、見晴らしの良い方の露天風呂で、他に利用客がいなかったのを幸い、足湯をして、ゆーっくり寛いじゃいました。
一つ、教訓を得ました。 八幡平は、車で行くに限ります。 バスと列車ではチト不便すぎました。1人が参考にしています
-

-

-

評価の内訳
部屋・設備 ☆×1
お風呂 ☆×5
食事 ☆×3
サービス ☆×2
1泊11700円ということで、ちょっと辛口になりましたが。。この立地を考えたら割高になるのは仕方ないのかな~?でも、たぶん1万2000円弱出すなら、もうちょっと設備のいい温泉のほうがいいかも。。
部屋は、6畳、風呂トイレテレビ一切ありません。窓はすりガラスで眺望も望めず・・・。はっきり言って部屋に長いこと居たい雰囲気ではないですね。
ご飯。さほど期待していなかった分、おいしかったです。てんぷらは、広間でその場であげてくれます。炊き込みご飯でおいしかったです。朝ごはんはちょっとさびしかったかな。
サービスははっきり言って皆無かと。お夕飯のときに漫談調の説明があるのが唯一のサービスでしょうか(面白かったけど)。全体的に、親切心が感じられない雰囲気でした。これも山の上だからしかたないのかな。
お風呂:これは文句なくすばらしいです。山肌に沿っている、混浴のほうの露天風呂が特にすごいです。今まで入った中でも、一番の濃さのある温泉だったかも!!女性専用エリアもあるので、ぜひ挑戦してみたほうがいいです。足元から沸いてくるタイプで、床には硫黄の泥がたっぷり・・・。泥パックしてました。
眺望のいい露天風呂のほうは、午後5時前ぐらいまでは日帰り客で芋洗い状態です。脱衣所もすごい混雑で全然ゆっくりは入れませんでした。宿泊の方は、5時過ぎか、朝チェックアウト前に満喫するべき!!
全体的に・・・
部屋がイマイチとか、設備がイマイチなのは仕方ない。あきらめますが、その割に11700円ってどーも高すぎな気がします。
ただお湯のパワーはすごいです。並じゃないです。
個人的には、日帰りで十分って感じかな~。少なくとも連泊はしません。1人が参考にしています
-

時々しか行けませんが、温泉は好きで、のんびりしたい休みの日には夫婦で出かけていました。そう今年のGWに藤七温泉のお湯に浸かるまでは。特に夫は、前の方が「足もと湧出の岩風呂風露天風呂」と呼んだお湯に感動し、「もう東京近郊の温泉はいい」とまで言い出す始末です。やはり温泉も自然の産物。山のいで湯が最高なのには、何の反論もできません。素晴らしかったです。
1人が参考にしています
-

-

-

-

-

2003年の夏、東北旅行の途中で立ち寄りました。
眺めのよい露天風呂と内風呂(女性用)のみの利用でしたが、
露天風呂の開放感はすばらしかったです。1人が参考にしています
-

八幡平山頂からも目視出来る距離にある秘湯で、電話会社(衛星電話を利用)にも電力会社(自家発電)にも見放された場所と宿の方は笑って自慢げに話してくれました。若旦那(自称:専務)が面白い方で、夕食の席に独演会みたいなのを開いて、宿泊客を笑わせてくれたのが印象的でした。
硫黄成分が含まれたお湯は疲労回復と共に湯上がり後もポカポカしていて非常にグッド!食事は質素ながらも、心がこもった逸品が揃い、美味しかったです。
早朝、有名なここの露天風呂から眺める朝日と岩手山のコントラストは個人的に忘れられない光景の一つで絶対にお薦めです!高地にあるため、露天から眺める眼下に雲がある何とも不思議な温泉です。1人が参考にしています
-

内湯も露天も素晴らしいですが、なんといっても
足もと湧出の岩風呂風露天風呂が最高。
お尻の下から湯玉がぽろりとわき上がる。新鮮この
上ない白濁した硫黄泉。素晴らしいの一言だけです。2人が参考にしています
-

籐七温泉と言えば、東北最高所にある温泉宿。情報誌に必ずといっていいほど取り上げられる有名な温泉ですが、実際写真で掲載されているのは岩手山を望む女性露天風呂、または男性露天風呂のどちらかだったと思います。私自身もその露天風呂だけを想像して行ったのですが、意外にも浴槽が他にもいっぱいあったのです。先に言った男女別露天風呂は内風呂と隣接しているので当然それぞれに内風呂がありますが、それは本館内の温泉だけです。敷地内に別棟があり、そちらに行くと男女別より広めの混浴内風呂、その外に広めの混浴露天風呂、さらに前方に歩いていけば(道路から晒し者になりますが・・・)、底から沸々と湯の沸く天然の浴槽があります。どれも白濁したトロトロの源泉が溢れており、いずれの浴槽も素晴らしい温泉です。混浴露天風呂の前を管理人(?)のおじいさんが「湯加減はどうですか~」と言って通りがかりました。こちらも思わず身を乗り出して「ちょうどいいですよ~」と答えました。本当にいい温泉です。
1人が参考にしています
-

昨年、新緑の頃、車で東北を旅した時に一泊しました。
八幡平展望台の駐車場から少し下った所にあり、展望台からもその赤い屋根を見る事が出来ます。
女性専用露天風呂からは岩手山を望む事ができて景色が最高!(男性専用の方は、それ程良くなかったと聞きました。)
ちょっと嫌だったのが、一緒に入っていた女性がタバコを吸っていたこと(あまりにも開放感があったからかもしれませんが・・・)。
宿の横にはポコポコと湧き出る源泉があって、そのせいか露天風呂の温度は結構高く、しばらく入っていると肌が真っ赤になる程です。
でも、ここで上がってその場で立ってはいけません。なぜかと言うと下を走る道路から丸見えになるからです。
まあ、あまり人も車も通らないかもしれませんが・・・。
こんな山奥なので夕食はぜんぜん期待していなかったのですが、期待以上の心のこもった食事で、
山菜をその場で天ぷらにするなどの工夫をこらしていました。
テレビもなく携帯電話も繋がらない、山小屋にちょっと毛がはえたような宿ですが、山の上の絶景露天風呂は最高でした。1人が参考にしています

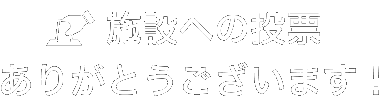
 閉じる
閉じる