フィンランドに行った時の話です。ご存知の通りフィンランドはサウナ大国で、そこかしこにサウナがあります。私はサウナも好きなので現地の方に「サウナがこんなにあって羨ましいです」と言いました。そうするとその方から「何を言ってるんだ。日本には温泉があるじゃないか。俺たちは温泉が無いからしょうがなくサウナに入ってるんだ」と言われたのです。
考えてみれば、日本には至るところに温泉があります。銭湯もあります。家庭にはだいたい、湯船があります。水資源が豊富ではない国にとって、浴槽に湯を張ってお風呂に入る、という行為はとても贅沢なものです。日本人にとっては当たり前の行為ですが、世界から見るとやはり特殊なのです。

サウナには確かにサウナの良さがありますが、湯には湯の良さがあります。その「湯の良さ」は当たり前の事すぎて見落としてしまうのかもしれませんが、その当たり前の尊さについて少し考えてみようと思います。
私が放送作家としてがむしゃらに働いていた頃。当時は人気番組に多く関わっていて視聴率も良かったのですが、「この仕事を続けても良いのか」と悩んだ時期があります。番組が人気になり、「視聴率すごいよ!」と褒めてもらっても実感が無いのです。視聴率は所詮、ただの数字です。勝った負けたで一喜一憂しても、その視聴率の向こう側に居るはずの人々の顔までは見えません。
だから、いくら頑張っても手ごたえが無いのです。多くの人に喜んでもらっている実感が無い。「仕事、辞めようかな」そんな事を考えていた時にまとまったお休みを取り、北海道に行きました。疲れていたのかもしれません。
そしてあれは十勝の銭湯だったと思うのですが、ふと立ち寄った銭湯でお風呂からあがると、脱衣所に置いたテレビに志村けんさんの「だいじょうぶだぁ」が流れていました。
その、当時ブラウン管のテレビに、小学生くらいの兄弟が競い合うように、かじりつくようにテレビを見ながらゲラゲラ笑っている姿を見たのです。「だいじょうぶだぁ」は私が関わった番組ではありませんが、近しい先輩が担当する番組でした。
「ああ、僕の番組もこうやって、日本中で、色んな人がゲラゲラ笑ってくれてるのかもしれない」と思い、「こんなに笑ってくれる人がいるなら、もうちょっと続けてみよう」とまた仕事に戻ったのです。

銭湯ではそこに住む人々の生活と、呼吸が感じられます。鏡の広告や、壁に貼ってある自治体からのちょっとしたお知らせ、漏れ聞こえてくる地元の方々の会話が、その街の「呼吸」を届けてくれるのです。だから、旅に行ったら必ず銭湯を探し、その湯に浸かって全身で街の呼吸を感じるようにしています。

京都にはかつて柳湯という銭湯がありました。昭和6年に建てられた渋い銭湯で、仕事場が近かったのでよく入りに行ったのですが、そのうち店主の方と顔見知りになり、「一杯どうです?」と声をかけられお風呂上りにビールを飲むのが習慣になりました。
それがエスカレートし、そのうち冷蔵庫にワインをキープするようになり、専用ロッカーを借りてワイングラスを常備するようになります。

閉店後、持ち込んだワインと店主の方が用意してくれたおつまみで飲み始め、そこに職場の仲間や近隣の方が集まり、何度となくみんなで宴会を開いたのは本当に良い思い出です。
柳湯さんは建物が古くても掃除が行き届いていて、本当に綺麗な銭湯でした。いつ行っても一番風呂かと思うくらい、タイルも浴槽も、湯もピカピカです。
長い間お兄さんがお湯を沸かし、弟さんが番台を担当していたのですが、お兄さんがお亡くなりになり、弟さんが「俺には兄のような湯は沸かせない」という事で廃業されてしまいました。柳湯にサウナはありませんでしたが、そこには綺麗な湯と、温かい人々がいました。

東京には滝野川稲荷湯という、有形文化財にも登録されている銭湯があります。柳湯と同じく、建物は古いけどとても綺麗にされている銭湯です。庭の池には鯉が泳いで、ペンキ絵は年に1回塗りなおし、ヒノキの桶はお正月に全て新品と取り替えられます。
年始最初の営業の日、水分を吸う前の桶から、「カーン」という乾いた、良い音が響くのを聞くと「今年も無事にお正月を迎えられたな」とお店の方は思うそうです。
ある日、少しあいた時間に稲荷湯に行くと、いつも番台に座っているお姉さんが居ません。「あれっ」と思って妹さんに聞くと、今朝、お姉さんがお亡くなりになったと。
「お姉さんがお亡くなりになったのに、お店を開けるんですね」
「お客さんには、関係無いからね」
遺族の方々が順番にお風呂の番をしながら、交代で病院に向かったそうです。ご姉妹は先代から「お客さんからお金を貰う以上は、感動させなければいけない」という教えを伝えられていたそうで、そんな時でもこの教えを律儀に守っていたのかもしれません。
この、湯に向かう姿勢が、掃除の行き届いたピカピカの浴槽を保ってくれるのです。

サウナで我慢して汗をかいて、その後に水風呂に入るジェットコースターみたいな爽快さは確かに湯には無いかもしれませんが、湯には体にかかる重力を減らし、力を抜いてぼーっと浸かる気持ち良さがあります。湯は、入った瞬間から気持ち良いんです。
そして湯に入りながら、ペンキ絵や鏡の広告、他のお客さんの所作を眺め、「コーン」という風呂桶の音に混ざって聞こえてくる会話をぼんやり聞きます。そうしている内、その土地の空気にすっかり包まれたような気持ちになります。

沖縄に現存する最後の銭湯「中乃湯」ではお客さんが軒先で三線を弾き、それに乗せて歌うおばあの歌が風に乗って聞こえてくることもありました。
私はもちろん湯が好きなのですが、突き詰めれば湯と、その湯にまつわる人々が好きなのかもしれません。そしてお風呂好きが高じて2015年から「湯道」を提唱し、さらに今回映画を作るに至ったのですが、現在公開中のこの映画『湯道』で描かれているのは湯と、湯にまつわる人々の物語です。

寒い日に入る湯の温かさ、手足を伸ばしてゆっくり湯に浸かる解放感、お風呂上りに飲む牛乳の美味しさ、お風呂を通じた家族とのコミュニケーションなど、身近にありすぎて当たり前になっている、湯が持つ魅力を少しでも表現できればと思い、作った映画です。

おかげさまでキャストの方々にも恵まれ、良い映画が出来上がりました。良い湯と温かい人々が出て来る映画です。映画を観終わったら、きっとその足で銭湯に行きたくなるはずです。ぜひ観てください。そして、湯の良さを知る人がもっと増えることを願っています。
映画『湯道』公式サイト https://yudo-movie.jp/
湯道百選公式サイト https://yu-do100.jp/
本記事は「ベストサウナ」ではなく「ベスト銭湯」をご紹介しております。サウナ好き、銭湯好きの方々に、いま一度「湯」の良さを知って頂きたく、「湯道」を提唱する小山薫堂様にご寄稿頂きました。湯の良さ、サウナの良さ、それぞれを楽しめるようになりますように。(ニフティ温泉編集部)
※この記事は個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません
写真提供:小山薫堂(映画「湯堂」ポスター画像含む)
取材・文:豊田佳高
編集:ニフティ温泉編集部

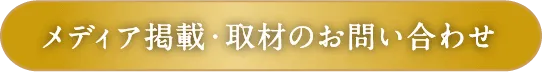


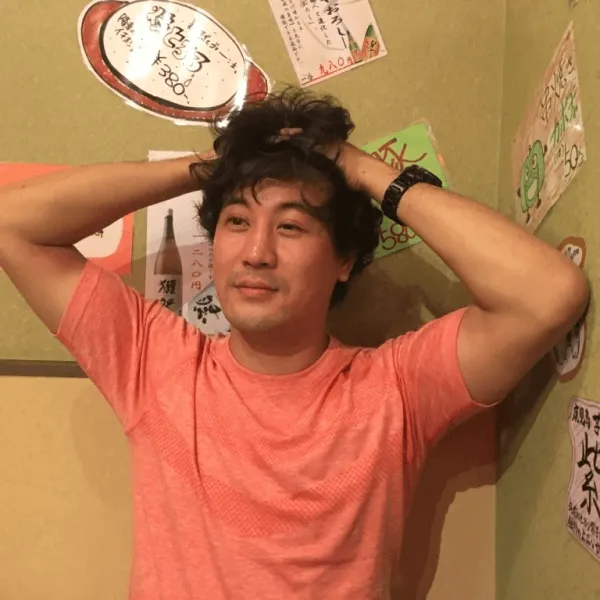










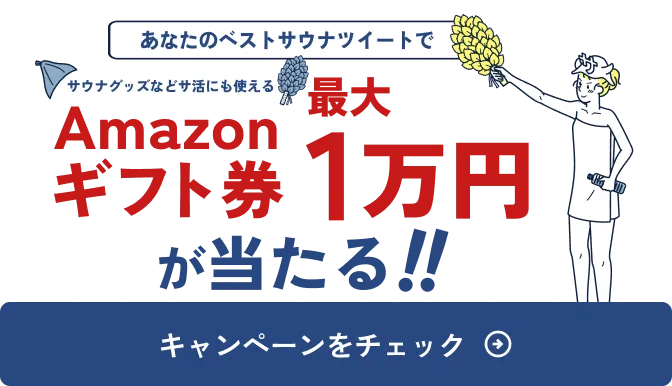
 サウナランキング2022
サウナランキング2022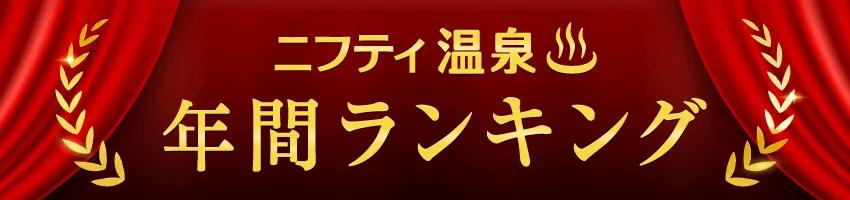 ニフティ温泉 年間ランキング
ニフティ温泉 年間ランキング